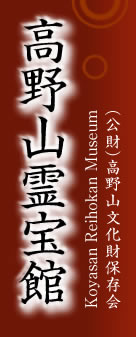彫刻(仏像)

- 国宝 諸尊仏龕 一基
- 金剛峯寺 中国唐時代
弘法大師空海が中国から請来されたと伝えるもので、七世紀頃の作。香木(白檀材)を三分割し、それぞれを蝶番でつなぎ、釈迦如来を中心にして諸菩薩などを細かく彫刻する。
両扉となる龕を閉じれば、携帯できるように工夫されており、枕本尊とも呼ばれている。

- 重文 不動明王坐像 一躯
- 金剛峯寺 平安後期
伽藍不動堂(国宝)の元本尊で、八大童子と共に祀られていた。左目をやや細め、口元からは上下の歯牙が露出している。痩身な体躯に、膝部に見られる流麗な衣文線など、平安後期の作風が見てとれる。

- 国宝 八大童子立像(矜羯羅童子像)一躯
- (運慶作)金剛峯寺 鎌倉時代
八大童子像の内の一躯。寺伝では建久9年(1198年)運慶の 作と伝えられており、その作技などからも運慶乃至は運慶 工房で製作された可能性は極めて高い。

- 国宝 八大童子立像(制多伽童子像)一躯
- (運慶作)金剛峯寺 鎌倉時代
伽藍不動堂本尊不動明王坐像と共に祀られていた八大童子像の内の一躯。不動明王の使者としての役割を担う。その凛々しい表情は、出色の出来映えを示している。

- 重文 大日如来坐像 一躯
- 金剛峯寺 平安初期
伽藍西塔の元本尊で、金剛界の大日如来である。
西塔は仁和三年(887年)に創建されたものと伝え、本像はその当初像と考えられる。高野山における数少ない平安初期像として大変貴重である。

- 重文 不動明王坐像 一躯
- 正智院 平安初期
檜材の一木造。頭に載せる蓮華(頂蓮)が大きく、両目を見開き、身構える姿勢が特徴。奥行きのある体躯からは重量感が伝わる。高野山に現存する不動明王中、最も古い雄作である。平安初期の作。

- 重文 孔雀明王像(快慶作)一躯
- 金剛峯寺 鎌倉時代
伽藍孔雀堂の元本尊で、後鳥羽法皇の御願により仏 師快慶が正治二年(1200年)に造立したもの。孔雀の背に乗るという絵画的な姿を、仏像彫刻として見事に完成させている。
ご注意
これらの宝物は、常時、展示されているわけではありません。
企画展・大宝蔵展に即して出品される場合があります。
画像の無断使用はできません。
このページは以上です。
Copyright 高野山霊宝館 All Rights Reserved