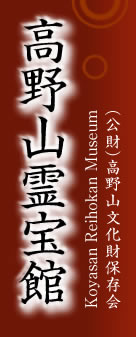高野山の史跡物件
史跡とは歴史に残る遺構などを意味します。

- 国指定 金剛峯寺境内
- 高野山の史跡指定は、大門を中心にした地域、壇上伽藍、金剛峯寺本坊境内、奥之院の四地域である。

- 国指定 高野山町石
- 古来より高野登山への表参道であった山麓九度山の慈尊院より大門までの道程に建てられた石塔婆で一町毎に合計180基が建てられている。さらに壇上伽藍より奥之院までが36基建てられている。本来は木製卒塔婆であったものを北条政子、安達景盛・義景・泰盛らの援助も得て弘安8年(1285年)現在の石塔に変更された。

- 県指定 豊臣家墓所(金剛峯寺)
- 奥之院参道御廟橋の数十メートル手前に位置する。豊臣氏は豊臣秀吉を創始者とし、その子秀頼の二代で絶えた氏。墓所には秀吉、母公、淀君らの一族が祀られている。慶長3年(1598年)に秀吉没。元和元年(1615年)大坂夏の陣で秀頼没。

- 県指定 禅尼上智碑(金剛峯寺)
- 禅尼上智碑は奥之院参道中の橋を過ぎ右側覚鑁堂にいたるまでの坂の途中右側にある。 碑は、高さ90.9センチメートルの砂岩で、碑文は上に梵字が一字あり、表に「(為)禪尼上智聖霊 奉造立沙(弥)蓮阿 永和元年乙卯七月日とあり、永和元年は北朝の年号で南朝の天授元年(1375年)にあたる。

- 県指定 高麗陣敵味方戦死者供養碑(正智院)
- 慶長四年(1599年)六月、鹿児島藩主島津義弘、忠恒の父子によって、朝鮮役における敵味方戦死者の霊を慰めるため、高野山奥の院の旧鹿児島藩主島津家の兆域の一隅に建立されている。

- 県指定 武田信玄・武田勝頼墓地(桜池院)
- 奥之院、中の橋手前、上杉謙信霊屋のほど近くに建てられており、信玄、謙信、両者の五度に及ぶ川中島の激戦は殊に有名である。勝頼は信玄の第四子として生まれ、天正元年(1573年)、信玄の病死によってその家督を継いだ。墓石には「俗名晴信 武田信玄公 恵林寺殿」と刻まれているのが、かろうじて読みとることができる。

- 県指定 崇源夫人五輪石塔(蓮花院)
- 寛永四年(1627年)建立。奥之院墓石群の中で最も高く大きいことから「一番石」とも呼ばれる(高6.6メートル)。崇源院とは徳川二代将軍秀忠の妻、駿河大納言忠長の母「お江与」で、本供養塔は忠長が建立した。お江与の方は、浅井長政とお市の方の娘、淀君の妹である。お江与の方は寛永三年(1626年)、54歳で没。忠長は寛永十年(1633年)、28歳で自刃。
このページは以上です。
Copyright 高野山霊宝館 All Rights Reserved